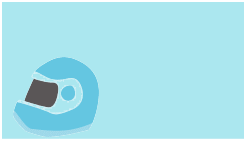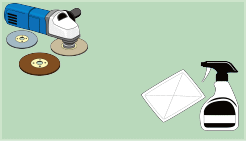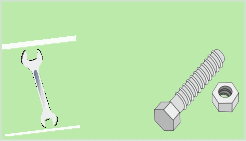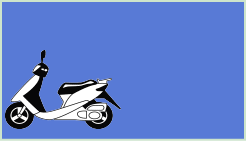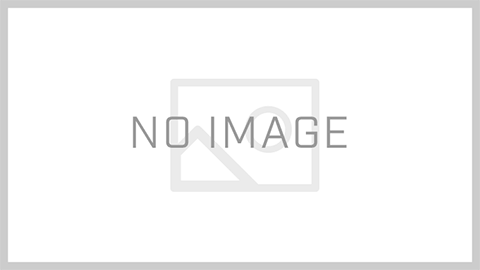小型(125cc)バイクは原付か?
原付とは原動機付自転車の略称で 50ccバイクをさします。

小型バイク=小型二輪は
道交法の用語では 2種類に区別されています
一般に使われる 用語の解説
- 原付き、原付き2種、
原付:50ccを指します
125ccクラスは 原付2種 または 小型自動二輪です - 小型、普通、大型自動二輪
原付きと自動二輪
= 原付き(原動機付自転車) :原動機(エンジン)が付ついた自転車
= 自動二輪 : 自動で走る二輪
125ccのクラスのオートバイは 二重制度の中に挟まれています。
125cc以下
| 免許制度 | 小型自動二輪 |
|---|---|
| 登録や管理 | (市役所、役場で登録) 原付2種 |
これ以上になる 自動二輪からは
126cc以上
| 免許制度 | 普通、大型自動二輪 |
|---|---|
| 登録や管理 | (陸運事務所で登録) 普通、大型自動二輪 |
になります。
つまり 125ccクラスのバイクは
- 免許制度では 自動二輪
- 管理上は(市役所、役場管理)の 原付 となり 区分で原付2種と呼ばれます。
妙に行政の管理と 免許制度の間に挟まれたバイクなのです。
だから呼び方も
- 排気量で 125ccクラス
- 免許制度で 小型自動二輪
- 登録管理で 原付二種
と呼べます。同じ125クラスを指すが、これらの呼び方は、一般にも、ネット上でも使われてる。
登録では原付に近い125cc(小型二輪)
登録は原付50ccと同様
自賠責などの保険も原付50ccと同様
登録場所も市役所、役場で、50ccと同様
ミニバイク特約では 125cc以下のバイクは 原付=50ccと同じ扱い。
免許では自動二輪な125cc(小型二輪)
免許制度では自動二輪です。実地試験がある。
原付のようにペーパー試験だけ、車の免許に付いてくる訳でなく、実地試験があります。
ほとんどの人が教習所でとるようです。
- 道に出ると自動二輪の扱いで、制限速度も250ccなどと同じ60km
- 違いは高速道路に乗れない程度の差。
妙に2重の制度に挟まれています。
最近は、小型2輪免許の取得がかなり緩和されました。
原付(50cc)のように、実地試験なしで乗れるようにの要望がかなり出ている。
特に、メーカーは50cc原付よりも、外国で売れている125を国内で売りたいらしい。
そこで、車の免許のある人には 最短2日 の教習所通いで取れるように緩和されました。
(原付みたいにペーパー試験だけ、はまだ先のようです)
続き、あわせて読みたい